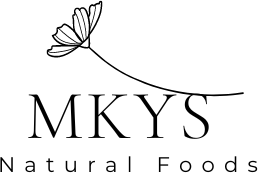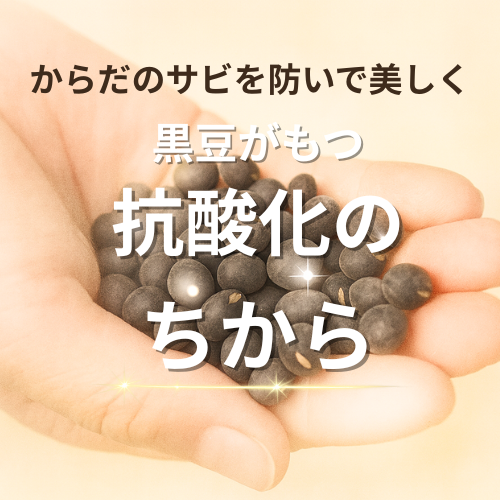お知らせ TOPICS
薬に頼らず、自然素材のだしで整える。からだの中から花粉ケア
薬に頼らず、花粉の季節を乗りきるために

春や秋になると、鼻のムズムズや目のかゆみ、のどのイガイガ…。
「またこの季節が来たな」と感じる人も多いでしょう。
花粉症の薬を飲むとラクになる反面、眠気やだるさを感じてしまったり、
シーズンが長く、飲み続けることに抵抗を感じることもありますよね。
そんなときに注目されているのが、薬に頼りすぎず、“からだの中から整える花粉ケア”。
そのカギとなるのが、「腸」と「免疫」、そして「食」です。
からだの中から整えるという考え方
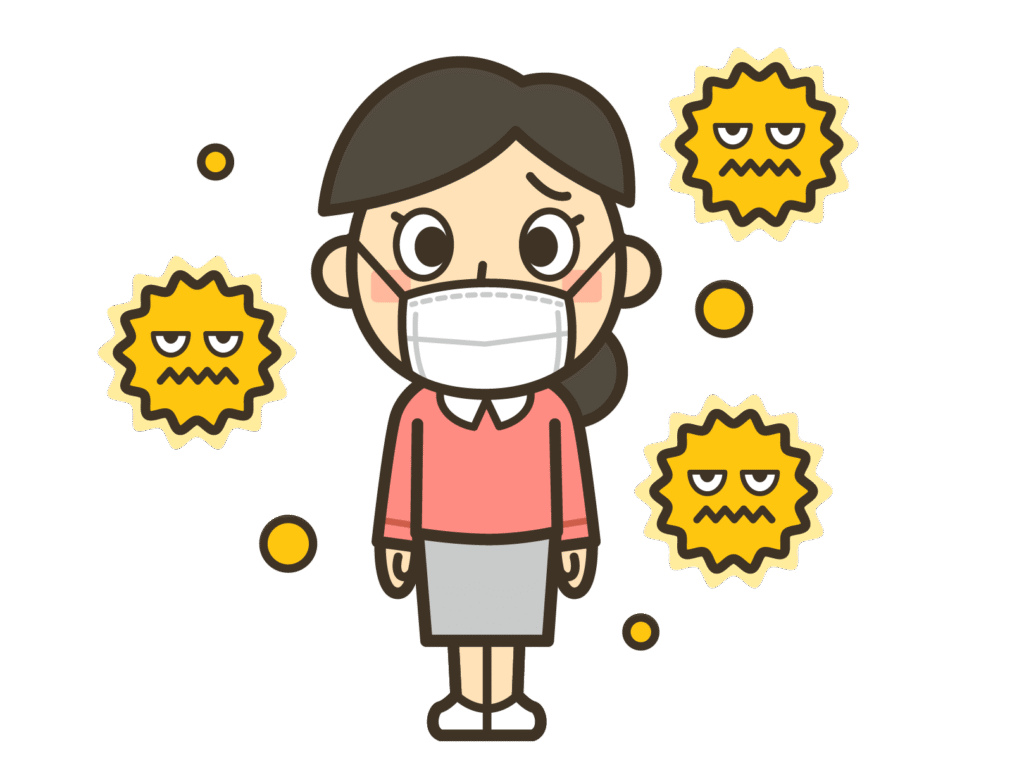
花粉症は、免疫が花粉を“敵”とみなし、過剰に反応してしまうことから起こります。
つまり大切なのは、「免疫力を上げる」ことではなく、“免疫のバランスを整える”こと。
そしてそのバランスをとるスイッチを握っているのが、実は「腸」です。
腸には全身の免疫細胞の約7割が集まっており、腸内環境が乱れると免疫の働きにも影響が出ることがわかっています。
だからこそ、腸内環境を整えることが花粉の季節を快適に過ごす第一歩。
そのためには、発酵食品や食物繊維を日常的に取り入れ、 腸の環境を整えることが大切です。
こうした日々の小さな積み重ねが、 “腸×免疫”のバランスを整え、花粉にゆらぎにくい体づくりにつながります。
そして、そのサポート役として注目したいのが、古くから日本の食文化を支えてきた「だし素材」です。
和のだし素材で“腸×免疫”をやさしく整える

だしの魅力は、「おいしさ」と「栄養のバランス」。
ここでは、花粉シーズンの体を支える代表的なだし素材を4つのカテゴリに分けて紹介します。
1.鰹節・鰯・飛魚に含まれるDHA・EPA
魚に多く含まれるDHA・EPA(オメガ3脂肪酸)は、体内で炎症のバランスを整え、免疫の過剰反応を穏やかに保つサポートをします。
2.昆布・寒天・菊芋の食物繊維
食物繊維は、腸内の善玉菌を育て、腸内環境を整えるのに役立ちます。腸を整えることは、そのまま免疫バランスを整えることにもつながります。
だし素材に多く含まれる食物繊維は、花粉の季節の“内側ケア”にぴったりです。。
3.椎茸・昆布に含まれるβグルカンやフコイダン
椎茸のβグルカン、昆布のフコイダンは、“粘膜バリア”を守るのを助け、鼻やのどなどの外的刺激から体を守るサポート成分としても注目されています。
だしを日常的に取り入れることで、粘膜のうるおいを守り、外の刺激に負けにくい体づくりを後押しします。
4.魚介や海藻に豊富なミネラル類
カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄など、だし素材に含まれるミネラルは、体の調子を整えるために欠かせません。
特に亜鉛やマグネシウムは、免疫細胞の働きを支え、花粉などによって乱れがちな免疫バランスを穏やかに整えるサポートをします。
日光×ビタミンDで、からだがよろこぶ自然のサイクル

腸や免疫を整えるうえで、もうひとつ意識したいのがビタミンD。
この栄養素は、免疫バランスの調整に関わる重要な役割を持っています。
ビタミンDは日光(紫外線)を浴びることで体内でつくられますが、魚や椎茸などのだし素材にも少量含まれています。
食事と日光の両方から取り入れることで、より自然に体のリズムを整えることができます。
朝の10分間、やさしい日差しを浴びることを意識してみましょう。
「365毎日おだし」で、和のだし素材をまるごと
だし素材を、日々の食事で無理なく取り入れられるのが「365毎日おだし」です。
鰹、煮干し、昆布、焼き飛魚、緑茶、椎茸、菊芋、寒天など、すべて国産の天然素材100%を使用。食塩・砂糖・添加物は一切加えず、毎日続けられる“やさしいだし”に仕上げました。
さらに、昔ながらの臼製法でゆっくり粉砕しているため、溶かすための化学処理は行っていません。
溶けないからこそ、だし素材そのものの栄養をまるごと摂ることができます。
毎日の料理にひとさじ。
味噌汁やスープ、煮物に加えて旨みをプラス
卵かけご飯・湯豆腐・納豆にふりかけて、調味料の代わりに
手軽に続けられる“だし習慣”が、からだの中からやさしく整える力になります。
購入はこちら。
小さな習慣で、からだは変わる

花粉に負けないためには、免疫のバランスを整えること。
そしてそのカギを握るのが、腸を整えることです。
そのためには、食を通してからだの中から整えることが大切。
出汁に使われる和の素材には、腸と免疫バランスを調える栄養素がたっぷり含まれています。
花粉症の新しい味方として、「だし」という選択を。
今日のごはんにひとさじ加えることで、腸と免疫の両方をやさしく支える“食からの花粉ケア”をはじめて、つらい花粉の季節を乗り切りましょう。